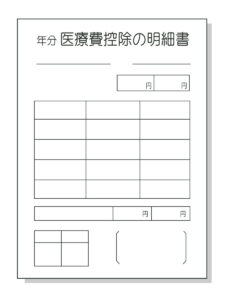介護の相談窓口・地域包括支援センターについて
市町村によって異なる介護相談の窓口
介護保険の相談窓口は(高齢福祉課)(介護保険課)(すこやかセンター)など市町村によって呼称が違うだけでなく、出張所が設けられていることもあります。そして
障害福祉や後期高齢者医療保険とは、別の窓口として設置され、保健師や社会福祉主事などの資格をもった職員が対応することも少なくありません。
介護保険の介護給付と保健福祉事業など内容ごとに窓口が別れている自治体もあります。
そうした縦割り行政にまつわる課題を指摘する声などもあり、高齢者の介護関係の総合相談窓口として、ほとんどすべての市区町村に設置されているのが地域包括支援センターなのです。
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターの責任主体は市区町村です。ただし、設置そのものは市区町村から委託を受けた法人も可能です。市区町村内に複数の地域包括支援センターがある場合は
その統括を担う(基幹型)を設置する場合もあります。
地域包括支援センターの役割は、被保険者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよるに支援することです。介護サービス、その他の保健医療サービス、福祉サービス、権利擁護のために必要な援助を利用できるように導くだけでなく、高齢者虐待の防止や早期発見などの権利擁護事業、支援困難ケースはの対応などのケアマネジャー支援、時には福祉事務所や児童相談所との連携など制度横断的な調整も行います。
設置の目安は第一号被保険者数3000~6000人につき、保健師等、社会福祉士等、主任介護支援専門員等それぞれ一人ずつの配置です。
地域包括支援センターと指定介護予防支援事業者の関係
要支援者のケアプランを作成する介護予防支援事業者となるには市区町村の指定が必要であり、その指定申請ができるのは地域包括支援センターだけです。